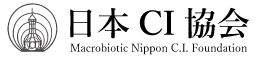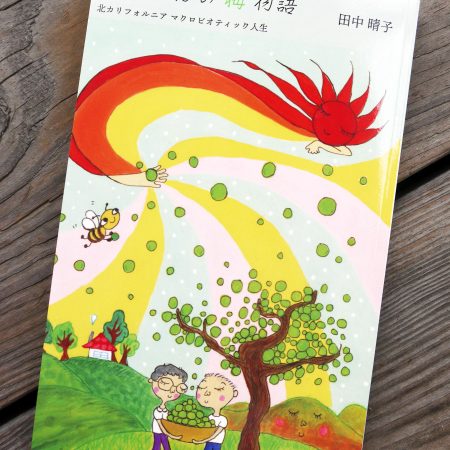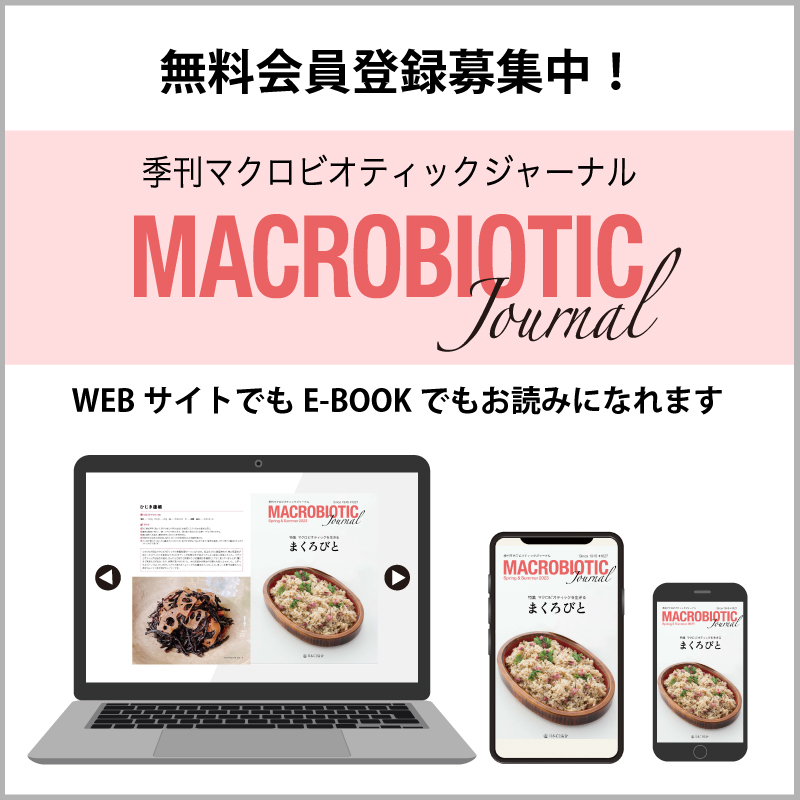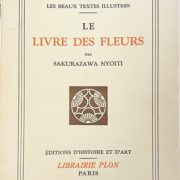【WEB限定記事】第5回マクロビオティック研究大会レポート

桜沢如一の誕生日に合わせた日本CI協会・正食協会共催の「マクロビオティック研究大会」が2025年10月18日に日本CI協会セミナールームで開催されました。
今年で5回目を迎えた大会は、正食クッキングスクールのベテラン講師小松英子氏とペルー出身でドイツに38年在住の講師イルマ氏が登壇、そして桜沢如一資料室メンバーによる「マクロビオティックという用語の起源と定義の変遷」というテーマでの共同発表が行われました。
マクロビオティック四住期 私の場合
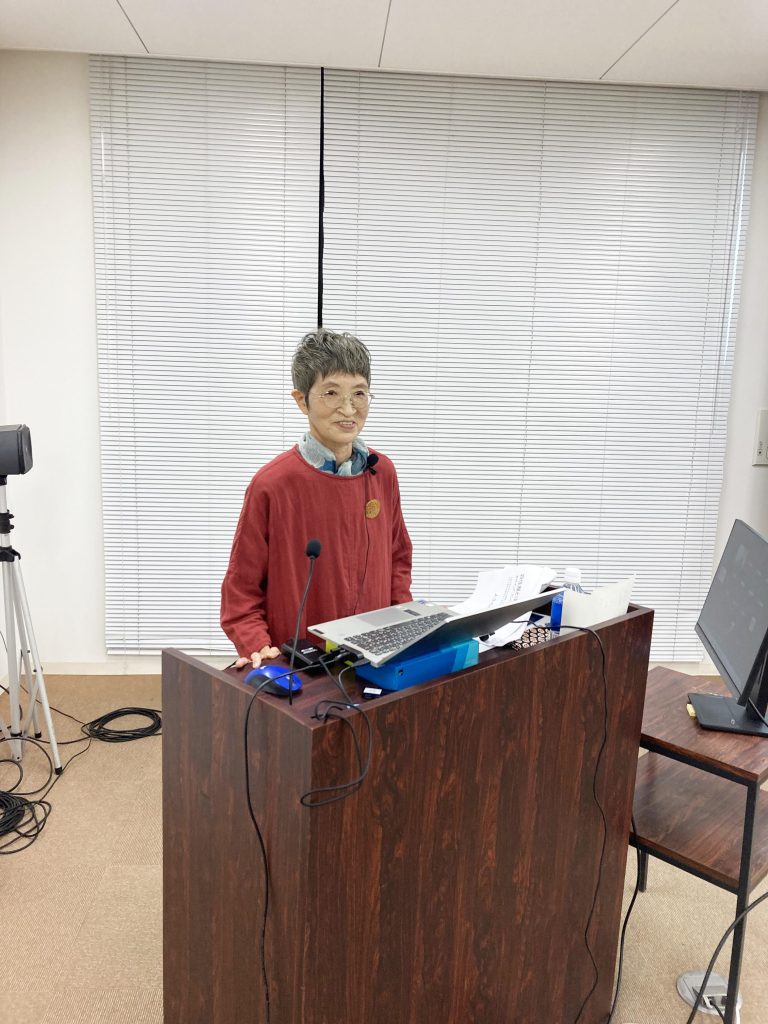
最初の登壇者である正食協会の小松英子氏は、ベテラン講師でありながら先日クッキングスクール リマのアドバンスⅡコースを修了しました。その探求心が存分に発揮された発表は、ヒンドゥー教の教えであり、人生の4つの段階を示す四住期の区分を使ったご自身の人生におけるマクロビオティック思想の深まりを語ってくれました。
桜沢如一の著書『食養人生読本』からの引用に照らし合わせたまさに小松英子版食養人生読本といった趣で、マクロビオティックは正食協会が掲げる生活の中での実践思想であることをあらためて教えていただきました。
現在、遊行期(75歳~)を迎える小松氏は、この時期を「食養家の老年こそ人生の最も平和な幸福な時」と位置づけ、「夢(目的)は食養に導かれ真の幸福となる(小松英子)」「我々の精神は全体なので我々の肉体はその部分にすぎない(桜沢如一)」「心食身一元論(高桑智雄)を全うする」「永遠に先んじる者は常に最後であれ(五福の考終命)」「知足者富(老子)」「感謝!感謝!感謝!」を大切にしていきたいとまとめました。
文化の架け橋としてのマクロビオティック:個人的体験、国際的な対比、そしてドイツの課題

二番目の登壇者で、ペルー出身でドイツのシュツットガルトに38年在住しながらマクロビオティックの講師を務めるイルマ・ユエン=ワグナー氏は、マクロビオティックわの会が主催する「第1回マクロビオティック国際交流会」への参加のため来日中で、当大会にも村井友子氏の通訳で発表をしてくれました。
イルマ氏はペルー、アメリカ、ドイツ、スペインなど世界での生活の中で、マクロビオティックを学んだ経験から、各国の文化の違い、そして桜沢如一、久司道夫、菊池富美雄などの系統を分類し、その特徴の違いをまとめてくれました。
そして、現在在住しているドイツでのマクロビオティックの現状と課題を詳細に報告してくれました。ドイツは「マクロビオティック」という言葉を作ったフーフェラントを輩出した国であり、シュタイナー思想やハーネマンのホメオパシーも盛んであるにも関わらず、肉食の伝統文化が根強く、なかなかマクロビオティック運動が広がらないのが現況だそうです。
しかし、国しての穀物生産量はとても多く、現在それらは家畜の試料となっているので、なんとか穀物中心の食文化への転換を進めたいとし、さまざまな発信のアイデアを提案してくれました。
ヨーロッパでもなかなか情報が入ってこないドイツの現状を詳しく知る貴重な機会となりました。
マクロビオティックという用語の起源と定義の変遷

三番目の発表は、今回始めての試みとなった桜沢如一資料室メンバーによる共同研究発表でしたが、予定していた高桑智雄室長、桑山一美氏、安藤耀顔氏のうち、安藤氏が体調不良により欠席となり二人での発表となりました。
まず最初に登壇した高桑室長は、インターネットやAI翻訳の精度の高まりから、世界各国の実践者や指導者・研究者との議論や交流が活発になっている現状で、その共通言語である「マクロビオティック」という用語がどのような定義で使われているかを把握すること、そして桜沢如一がどのような意味で使い始めたかという歴史を認識することは、国際的なネットワークを確立する上で、とても大切なテーマだと問題提起を行いました。
例えば日本CI協会から発行されている『マクロビオティックガイドブック』には、「MACRO(大きい・長い)+BIO(生命)+TIC(術・学)」を意味するとされていますが、これらがどういう経緯で定義されたかはあまり知られていないそうです。そこで高桑室長は、「用語の起源」「桜沢如一の使用事例」「桜沢以後の定義の変遷」という3つのテーマで論を展開していきました。
高桑室長のまとめとしては、「マクロビオティック」という用語は、18世~19世紀のドイツの医師、フーフェラントによってはじめて使われて、桜沢が1929年に渡仏した頃には、欧米では「マクロビオティック」という言葉は「長寿法・長生法」といった一般名詞として知識層の間ではよく知られた用語だったそうです。
桜沢が本格的に「マクロビオティック」という用語を欧米で使いはじめたのは1960年代で『ゼン・マクロビオティック』の出版が契機となったそうですが、そこでも桜沢はあくまで日本で使っている「正食法」の訳語としての使用で、現在のような「マクロビオティック」が桜沢の宇宙の秩序、無双原理のような思想・哲学、そして大いなる生命の術のような広大な概念ではなかったそうです。万人が高尚な思想や哲学を考えずとも簡単に実行できる実践法としての「正食」を「マクロビオティック」と訳したそうなのです。
それが、大いなる生命の術といったような広大な生命観・宇宙観に定義を広げていったのは、海外で活躍したヘルマン相原や久司道夫、そして日本の後継者たちであったと論じました。

共同発表の二番手は資料室司書ボランティアの桑山一美氏による『Zen Macrobiotics』における英文用語使用例まとめでした。桑山氏は、同書の中の「マクロビオティック」という用語がどんな意味で使用されているかを分類し、56.4%が実践手法としての使用であり、その意味で高桑室長が論じる桜沢が「マクロビオティック」という用語を実践法である「正食法」の意味で使ったということは論証できるとします。
しかし、現代の「マクロビオティック」という用語には、食養や対症療法としての意味もあり、神秘思想や個人的世界観など何でもありの曖昧な状況を整理するために、あらためて正食、無双原理、宇宙の秩序という桜沢思想を「マクロビオティック」として定義し直した方がよいのではないかと提言しました。
高桑室長は、桑山氏の発表を受けて、桜沢は万人がいつでもどこでも実践できるものとして、深遠な哲学や思想を前面に掲げない「正食法」を世界に広げたかった。その「正食法」の訳語として「マクロビオティック」という用語を使用したのだから、後世の私たちが、「マクロビオティック」という用語を深遠な哲学や思想にしてしまっていいのか?というのはこれからの議論のテーマになると言います。今回の発表があらためて皆さんにとっての「マクロビオティック」の定義を考えるよい機会になればとまとめました。
天国の「狭い門」の3つの鍵

最後に、来日中のアルゼンチンのマクロビオティック講師であるヒメナ・アルバレス氏が登壇しました。
ヒメナ氏は、現在ご自身が感じているマクロビオティックで大切な三つの視点を語りました。一つ目は「責任」で、これは陽性な姿勢を示すものです。健康と人生を変えるのは自分なのだという責任です。二つ目は「マインドセット」で、無双原理(社会の信念体系全体を覆す)に基づいた新たな思考様式を構築する必要があり、これは陰性な姿勢を示すそうです。最後の三つ目は「信じること」であり、それは知ることによる信仰であって、盲目的な信仰ではないとのことです。これは一つ目と二つ目の陰陽が調和して初めて示される姿勢だそうです。
ヒメナ氏の陰陽両面を大切にする大観的なメッセージは、参加者に大いなる感銘を与えてようです。
今年も4時間にわたる熱いメッセージが語られた研究大会となりました。お申込み数も会場参加、オンライン、アーカイブ合わせて130名を超えて、マニアックな内容でもあるに関わらず大きな注目を浴びました。
まとめとして、共同開催の正食協会の岡田恒周代表が挨拶をし、今後の大会の発展を祈願しました。
登壇者のみまさま、参加者のみなさま、開催にあたって準備をしてくれた関係者のみなさん、ありがとうございました!